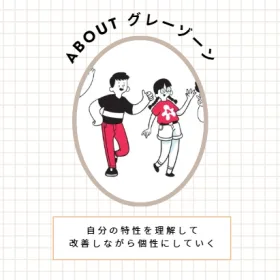こんにちは、名古屋こどもカウンセリングとSST教室のしらいしです。
安心できない状態を表す「不安感」はわたしたちにとてもなじみのある感情であり、多くの場合「負の感情」として扱われます。
軽いものや一時的なものであれば問題ないと思いますが、強い不安感や慢性的に感じる場合は、日常生活に支障をきたしてしまいます。
こどもの不安にもいろいろな形があり、説明しながら対応できるカウンセリングや療育的なアプローチを紹介していきます。
※かんじがよめないおこさまやおんせいでききたいばあいは、こちらのぶんしょうをクリックしてください。(音声読み上げ案内)
不安と恐怖の違い
医学的には、
- 具体的な対象があるものを「恐怖」
- 具体的な対象がないものを「不安」
として違いが述べられています。
※不安も恐怖も同じものとして理解されたら良いという考えの先生もおられます。
ですが一般的な認識では、
- 強い恐怖感情は「恐怖」
- それより少し弱いものを「不安」
と捉えている方もいらっしゃったり、
- 目の前にある怖さを「恐怖」
- 少し未来にある恐怖を心配して感じるのが「不安」
と感じる方も少なくありません。
いろいろな捉え方がありますが、そういった見識を踏まえ、包括しつつ、この記事では「不安」を述べています。
こどもの「不安」のいろいろ
子供が感じる「不安」には、いろいろな形があります。
乳幼児のころは、興奮の一つから感情はスタートし、、快と不快の2種類を追加し、発達に伴って様々な感情を感じられるようになります。
最初に不安という感情を感じるのは、「分離不安(ぶんりふあん)」といわれています。
愛着のある母親や信頼する人と離れることには誰でも最初は不安を感じるものです。
その不安は安全を確保するうえで必要な場合がありますが、長期的に続くと探索するための自立を阻んでしまうこともあります。
次第に成長していく中で暗闇やおばけ、悪夢、危険生物に恐怖や不安を感じるようになり、死に対する恐怖や不安に発展していきます。
それらの不安や恐怖になれて、ある程度理解や受容をしていきながらも社会的な理解が進み、嫌われることや仲間外れにされる人間関係における恐怖や不安を感じるようになります。
ようするに「社交不安」を感じられるようになります。
また漠然とした不安を感じる「全般性不安症(全般性不安障害)」などでは、いろいろな活動や出来事に対して不安や神経質に感じることが増えてしまいます。
こどもの不安の種類
こどもの不安の医学的な種類としては、
- 分離不安
- 社交不安
- 全般性不安
- パニック
- 限局性恐怖症(対象のある:ヘビや高いところなど)
- 広場恐怖症(助けを得られない、逃げたりできない状況でのパニック)
などがあります。
もう少し一般的な言葉に不安症状を言い換えると
- 新しい場所に対する恐怖や不安
- 母子分離ができない
- 誰かがそばで守ってほしい欲求が高い
- 見通しがわからなければ不安がる
- 人とのコミュニケーションに不安や苦手意識が強い
- 混乱してパニックになることがある
- 漠然とした不安がある
- メルトダウン(発達障がいや知的障がいに多い)
- 男の人に(女の人に)恐怖や不安がある
- 暗闇を怖がって不安がる
- 悪夢を怖がって不安がる
- 死ぬのを怖がって不安がる(自分や親が)
- 新しい人との出会いを怖がって不安がる
- 強い愛着行動を示す(過剰な接近や抱き着きor対人関係拒否)
- 新しい行動を不安がって実行できない(時間がかかる)
- 学校恐怖症や嘔吐恐怖症、IBS(過敏性腸症候群)
- 場面緘黙やうまく言葉がでにくい(発表で緊張し過ぎる)
- 不安がって積極的になれない
- 不安がってネガティブに捉えてしまう
- 不安で苦手なことはやりたがらない
- ありもしないことを大きく怖がり不安がる
- 不安がって神経質になる(強迫的になる)
- そわそわする・多動になる(不安によって)
- 不安が強い時に問題行動がでる(自傷他害、常同行動)
- 嫌われるのが怖くて対人関係に不安がある(いじめや仲間外れ)
など様々な症状があります。
太古の人間社会であれば、
地震や戦、猛獣、危険場所、危険人物を避けるために恐怖や不安は身の安全を守るために役立ちました。
避けることで身の安全を確保しやすいものばかりでした。(地震は災害対策のリスク低減をするうえで)
しかし不安になるものが人間社会や人間関係になると再遭遇することが多くあります。
不安になる⇒避ける⇒苦手意識・不安対象は変わらない⇒また不安が想起される場面に出会う⇒不安になる
といった負の循環が起き、避けるだけでは困難な循環に苦労することが増えてしまいます。
近代では、不安に対して
- 克服したり
- うまく対処したり
- 認知を変えたり
- スキルを獲得したり
- 不安が出やすい精神や身体にアプローチしたり
- 不安感情をうまく扱えるようにコントロールしたり
しながら乗り越えていかなければならないことが増えています。
不安の感じやすさの違い
不安は、
- 感じやすい場面の遭遇の多さ
- 感じやすい特性(遺伝や認知)
- 環境や生活習慣
などにより感じやすさに変化が出ます。
例えば失敗が少ない人は、機会的に「また失敗するかも。。。」という不安は起きづらいということです。
逆に失敗しやすい人は失敗したときにストレスを感じ、同様の行動を行うときに不安を感じやすくなります。
しかしストレスの感じ方は人によって異なり、その失敗のとらえ方など認知的な評価によっても不安の表出に影響を与えます。
また普段不安を考える時間の有無や生活習慣、自信や自己効力感などによってもそれは変動します。
不安を感じやすい人が不安の出やすい行動を多く起こし、日常で不安を感じられる時間も長く、自信や自己効力感を上げる機会が少ない場合は、非常に不安の表出が多くなりやすいということです。
適度な不安は適度な緊張感を生み、集中力が増して成果を出しやすい状態になるといわれています。
不安はある程度であれば(認知的な捉え方にもよりますが)良い側面もあるということです。
しかし不安が強くなれば、その行動を回避し、苦手意識を強めて、克服の機会を無くしてしまいます。
また強い不安により、パニックや強迫症のような症状に悩まされてしまうこともあります。
こどもの不安症状のいろいろ
精神症状としては、
- 不安感がある
- 心配してしまう
- うまくいかないと思い込んでしまう
- 失敗やうまくいかないイメージをしてしまう
- 逃げ出したくなる
- 緊張する
- 焦ってしまう
- 動揺してしまう
- 自信がなくなる
- 落ち着かない
- イライラしてしまう
- やる気が出なくなる
- 挑戦できない気持ちになる
- ふさぎ込んでしまう
- 閉じこもりたくなる(ひきこもりたくなる)
- 自分や他者を責めてしまう
- 抑うつ
などがあります。
身体症状では、
- 心臓や胸がバクバク、ぞわぞわ、キューっと締め付けられる感じがする
- おなかの調子が悪くなる(胃痛、腹痛、下痢、吐き気など)
- 力が入らない(または筋緊張、しびれ)
- 震えてしまう
- ひどくなると失神
- 頭痛や頭が締め付けられる感覚
- 頻尿やおもらし、夜尿
- めまい
- 息苦しさ
- 汗がでやすい
- 自律神経失調症状が増える
- 多動、じっとしていられない
- パニック
- 強迫的な症状
などを感じることがあります。
ですので不安の精神症状や身体症状が出ることが不安という「二重の不安構造」で苦しむことが起きてしまうことがあります。
脳の前頭葉と「不安」
不安感情が湧くと脳の中ではノルアドレナリンが分泌されて、
集中力を上げて、戦うか?逃げるか?時にフリーズするか?を判断させます。
そのため不安感情を続けていくよりも「行動」した方が良い場合が多くあります。
歯磨きをする、お風呂に入る、など何でもよいのです。
また不安が言語化することによって扁桃体の働きを抑制させることができることも分かってきています。(難しいことは私のカウンセリングなどで行っています)
さて高次機能を司るといわれている脳の前頭葉の発達が進んでくると、
- 感情のコントロールがうまくなる
- 計画性を持てる
- 意欲や気持ちの切り替えができる
- 創造性が高まる
- 集中力や注意できることが増える
- 動機付けで意欲を変化させることができる
- 遂行力や実行機能がうまく働く
- 過去から学ぶ
- 時系列で考えることができる
- 怒りの感情などを抑制できる
などができるようになるといわれています。
ですが、これが成熟するのが25歳前後といわれています。
こどもの頃は、感情のコントロールや制御が難しかったり、行動に結びつける遂行力や実行機能も未熟であったりします。
ですので大人になった私たちも忘れているかもしれませんが、他者から見るととても小さなことで強い恐怖や不安を感じることがあります。
ASDやADHDなどの発達障害などでは、前頭葉の発達の遅れが指摘されるケースがあるため、この不安の感情によって日々の生活に支障をきたしてしまうことも少なくないとされています。
脳の前頭葉の発達を促すことができれば、不安をうまくコントロールできる脳機能の発達が期待されます。
当相談教室では、それを実現すべく心理カウンセリングや療育的なアプローチを組み合わせて対応しております。
こどもの不安に対応できるアプローチ
こちらで行っております、こどもの「不安」に対するアプローチを紹介します。
以下様々なアプローチは時間をかけてアセスメントを行い、必要なアプローチを組み合わせていきます。
①心理カウンセリングによるアプローチ
カウンセリングでは、必要に応じてまずは安心できる環境を整えます。
そして不安に関する内容を聞き取りながら
- 何が不安を感じる原因になっているか
- どのように要因が絡み合っているか
- それは自分で理解できていたかどうか
などを一緒に話しながら、自分の不安について理解を深めていきます。
理由はひとつだけではなく、複雑に絡み合っていることも多くあります。
それらの原因や要因がわかってきたらそれを解消するように進んでいきます。
おおもとの根源の部分をぐっと乗り越えると大きな精神的な成長を感じられ、怖さや不安に変化がみられていきます。
不安症は不安の正体が見えてくると心理的に安心しやすくなる場合があります。
しかし原因がうまく出てこない場合もあります。
そういった場合も漠然とした不安感が出る要因となったところにアプローチをしていくと変化をしていく場合があります。
また不安の原因ではなく、機能的な意味をみていくと改善につながっていくケースもあります。
不安症は、不安や心配ものを克服するだけでなく、本来の自分の状態へ回復していくような手順も重要になることがあります。
心理カウンセリングはお子様の認知機能の成長によって視覚的な理解を促しながら行うケースや大人と同様の手順で行う場面など幅広く利用できるように工夫しております。
②SSTによる対応
SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)では、人とのかかわりの中で対人スキルを獲得することでその関係性の問題を解消させることに役立ちます。
信頼できているカウンセラー(トレーナー)と一緒にスキルを獲得していく中で自信や自己効力感を向上させることもできます。
③身体的アプローチ
不安の相談ケースでは、自律神経系が乱れてしまっていることも少なくありません。
そういった状況で身体的なアプローチを行うことで自律神経に良好な影響を与えるセッションを追加できます。
また身体操作から不安にアプローチしていくワークなども有用な場合があります。
➃感覚統合的アプローチ
人間の発達には非常に個性が多く、発達が遅れていながら成長することがあります。
そのためうまく機能できていない脳神経系が「不安」を助長させてしまうことがあります。
そういった場面でも感覚統合的なアセスメントを行い、アプローチを行うことで変化が期待できるケースもあります。
➄愛着アプローチ
愛着形成は非常に複雑です。
保護者が与えていてもうまく受け取れていない場合、欲しい愛着刺激が得られない場合もあります。(ですので誰が悪いとかの問題ではない)
子供が欲しい愛着刺激を探し、ご家庭と連携したり、代理しながら「安心感」「安全感覚」「探索できる自立心」の形成に役立てます。
参考文献:小児の全般不安症 前頭葉(ウィキペディア)
名古屋市で行っている「こどもの不安に対するアプローチ」

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
基本的なご利用料金は「個別セッション(約55分フィードバック含む)6000円」になります。
場所は愛知県名古屋市昭和区川名です。詳しくはこちらへ「アクセス」
空き状況は変動しますが、目安としてはトップページ下部に載せています。