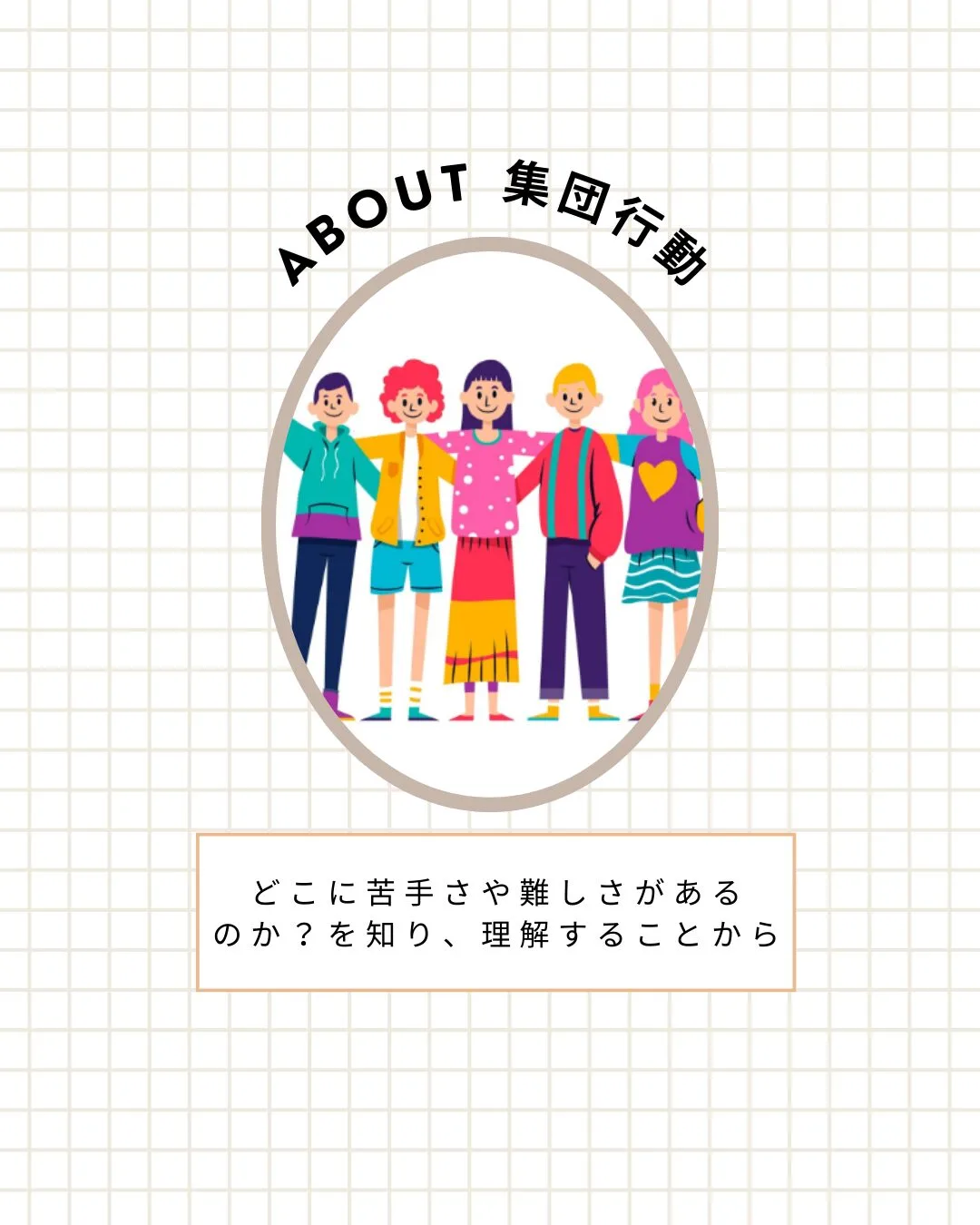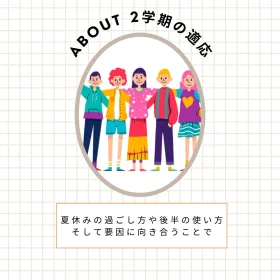集団行動が苦手。。。
集団になると指示が入らない。。。
不適切な行動が増えてしまう。。。
集団やグループに入っていけない。。。
集団がそもそも苦手。。。。
集団行動の苦手さは、大きく分類すると精神的な問題で難しさを感じる場合と発達的な課題で難しさを感じる場合があります。
精神的な課題と発達的な課題では全く異なる理由があったり、アプローチも異なることが多くあります。
そのお子さんによって理由に違いがありますが、この記事では、集団行動の苦手さとカウンセリングや心理療法、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、療育でできることについてまとめて書いていきたいと思います。
その分、お子さまの内容に適合するパートとそうでないところがありますので飛ばしながらお読みいただけたら幸いです。
集団や集団行動の苦手さと原因(理由)
集団になると
問題行動が増えたり、
指示が入らなかったり、
うまく適応できなかったり、
苦手意識があったりすることがあります。
園や学校は、集団が基本になります。
そのため集団行動が難しくなると、苦痛な時間もその分増えてしまいます。
そして行き渋りや不登校(不登園)などにつながってしまうこともあります。
集団内において、本来その子の持っている能力がうまく発揮できなかったり、苦手意識を持ってしまって、集団に適応できなくなることもあります。
そもそも、どうして集団が苦手なのでしょうか?
なぜ集団行動が難しいのでしょうか?
それは人によって要因や原因などの理由は異なります。
また、ひとつの影響だけでなく、複数の要因が影響しあっている場合もあります。
それでも何が影響しているのかを理解していくと、改善したり、配慮したり、克服することに非常に役立ちます。
また原因を子供に帰属させすぎて問題を大きくしている場合には、その帰属を変化していくことでその影響も出てくるかもしれません。
集団や集団行動が苦手な理由をここに挙げていこうと思います。
- 注目が欲しい気持ちが強い
- 自己中心性が高い(自分が一番、好きなようにしたい欲求が高い)
- ルールが嫌い、苦手(自分がしたいようにしたい)
- 衝動性や多動性が高い(ずっと座れない、興味があることに衝動的)
- あまのじゃく特性がある(みんなと同じようにしたくない欲求が高い)
- 普段から縛られることが多くて縛りに反発したい
- 我慢や行動制御が苦手
- 他者に興味を持てない、一緒にやることに興味を持てない
- 刺激が多すぎてつらい(いろんな声が入ってくるなど)
- 静かな環境を好む
- 一人の世界を好む
- つまらないと上の空やマイワールドに入る、刺激を欲する
- プライドの高さ、理想の高さ
- 劣等感が強い、優越コンプレックス
- 集団内での傷つきやその不安がある(いじわる、恥ずかしい出来事)
- 社交不安や対人恐怖がある
- ペースを合わせられない
- 人の目が過剰に気になる、人の目を一切気にしない
- いじめやいじわる、喧嘩の影響
- 自分の捉え方や受け取り方(認知の問題)
- 不安が強い
- 分離不安(一人でできることが少ない)
- お家の環境が良すぎて離れられないケース
- 基本的な対人の信頼関係がうまく築けない
- やってもらって当たり前な精神状態
- 感覚過敏や鈍麻(刺激の受け取り方の特性がある)
- 見通しが見えない不安と急な変化に混乱や強いフラストレーションを感じる
- 攻撃性が強い
- 対人コミュニケーションスキルの獲得がうまくできていない
- 感情理解やコントロールが難しい
- 身体的な特性
- 快楽が強い遊びの影響(脳が快楽報酬を欲する)
- 過剰に適応し過ぎて疲れる
このように
発達の課題
性格やパーソナリティの影響
環境の影響
精神的な課題
身体特性
関係性の問題
スキルや経験の不足
遊びや報酬の影響
人生のとらえ方
いろいろな影響や課題があります。
ひとつずつ丁寧に改善、獲得、克服していくことで、集団や集団行動への適応が進んでいくと考えられます。
指示が聞けない
指示が聞けない場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
発達的な課題では、
- つまらない、楽しくない、などの感覚理由から上の空になっている
- 自分の世界観やマイワールドに入っている
- 今集団で行っていることに興味を持てない、注目できない
- 注目が欲しい
- 衝動性や多動性があって落ち着かない、聞くことができない
- 注目を続けられない、集中が続かない
- ワーキングメモリーの問題で忘れてしまう
- その子に合った指示が口頭指示ではまだ難しい
- 焦点を合わせてもらって指示しないとうまく情報が入らない
- 自分の中での正解やこだわりが強い
- 不安が強い
- 応答する力や経験が不足している
などがあるかもしれません。
精神的な課題では、
- 指示されることへの抵抗感が強い
- お試しや愛着的な行動特性
- わざと指示を聞かない
- 考え事や悩み事がある
- 人の目が気になる
- あまのじゃく特性
などがあるかもしれません。
どちらの課題にしても指示を聞いて、その通り行動するには、その子なりの課題をクリアしなければ難しいことが多くあります。
問題行動が増えてしまう
集団になると
- フラストレーション(ストレス)が溜まる
- 拒否したい気持ち、動きたい気持ちが言葉よりも行動で出る
- 我慢が多くなる(抑圧も増える)
- 妥協できなければ、受け入れできなければ余計につらい
- 注目してほしい欲求や愛着欲求
- つまらないといった不満の気持ちが高まる
- 社会性の中でのストレスを感じる(コミュニケーションや勝ち負け、譲歩)
- 勝ち負けやうまくいかない、失敗のストレス
- 恥とプラインドの問題
などの理由で問題行動が増えてしまうことがあります。
またその行動で注目され、それが報酬となってその行動が増えてしまうことがあります。
問題行動の内容にもよりますが、できるだけ早く修正を余儀なくされることが多くあります。
そのため本人も怒られることが増えて、二次的な問題でそれを強めてしまう結果になってしまうこともあります。
ここでもやはり「理解」がベースになります。
なぜそれが難しくなっているか?
なぜその問題行動が必要なのか?
何を訴えようとしているのか?
その視点から進めていくとよい方向に進めることが増えていきます。
分離不安と精神的自立
最初は母子分離と精神的な自立が基本になることがあります。
お母さんや保護者がいなくても安心できる自分になるには、人によって手順も異なります。
実際には何度も引き離される経験(よく園であるように)を通して分離が自然とできることが一番多いかもしれません。
しかしそのまえに家でできることとして、お母さんが見えなくても大丈夫な状態を練習できると園などへの適応の練習としてよい場合があります。
母子分離不安はいろいろな形があります。
- お母さんや保護者がいないことがさみしい、心細い、理解できないことで起こる場合
- 母子の関係性のかかわり方で起きる場合
- 元来のお子さまの不安感や自立心の特性の影響
- 園でうまく適応ができない、不安、うまくいかない経験の連続、欲求が通らない連続
- 家とのギャップが大きすぎる場合
- 欲求や要望が強い場合
- 受け入れる力や妥協が弱いケース
いろいろある中でどこにその要因があるかを知ることで不安の解消や改善の方法が異なります。
母親が見えなくても、この世に存在していることが理解できていると少し安心できます。
でも「お母さんは自分のそばにいるべきだ」という強い欲求があると、この理解があっても分離不安的な症状が出ます。
このように子供の捉え方や受け入れる力、欲求などにも目を向けなければいけません。
精神的な自立ができていなくて集団行動が苦手になっているケースもあれば、自立はできているが違う要因で集団行動に苦手さを感じる場合があります。
注目が欲しくて難しくなるケース
- 注目が欲しい
- かまってほしい
こういった気持ちが強くて集団行動が苦手になるケースも多くあります。
怒られたり、注目されると余計に楽しくなったり、良い気分になったりします。
集団に慣れていない場合も良く起こります。(その場合は少しずつ慣れてきて、こういうときはこうするんだ、と適切な認識が持てれば改善することが多い)
- 自分が絶対一番
- 自分の思い通りにしたい
- 自分が優位でなきゃ許せない
などの自己中心性が強い場合も集団行動に支障が出ることもあります。
なぜ注目を欲しがったり、
自己中心性が強く出ているのか?
その子なりの理由がありますので
そこを理解したうえで、ご家族とも協力しながら進めていくことが大切です。
縛りやルールが窮屈で嫌い
縛りやルールが窮屈で嫌いになってしまうこともあります。
- どのような環境で生活しているか?
- 妥協する力(社会的妥協)
- どのような不満と要求があるか?
を理解したうえで少しずつ練習できていくといいですね。
必要に応じて環境調整も大切になることがあります。
お子さんによっては
- おふざけが強く出てしまう
- あまのじゃくな行動が多い
という場合もあります。
問題行動ではなく、言葉で本当に言いたいことを伝えることも大切なプロセスになることがあります。
発達課題の場合は個別療育で行動学習で少しずつ慣れていく方法がとれるでしょうし、精神の場合はそのきもちを理解してもらうことからスタートしていく流れになるかと思います。(発達の場合もそのなぜ?を理解できることが大切です)
衝動性や多動性などの要因も療育の中で行えることはたくさんあります。
集団に基礎となる「個別療育」
発達に課題を感じるケースでは、第一選択として「療育」が選ばれることが多いと思います。
療育的には、
個別療育で基礎を作って
集団へ進む
といった考えがあります。
個別療育とは、先生と1対1で注目された状態で行う療育です。
ここで指示を聞けることが増え、行動の制御を行いながら、楽しく学ぶ基本を身に着けます。
その基礎を作ったうえで、少ない人数の小集団へ進み、大きな集団へと適応できるようになっていきます。
1対1の個別の療育でしっかり集団行動の基礎になる
★コンプライアンス(指示に応答できる)
★ルールの理解
★やり取りとコミュニケーション
★感情コントロールと行動制御
などを学ぶことができるといいですね。
「人の目が過剰に気になる」と「一切気にしない」
人の目が過剰に気になると相手にどう思われるかが気になってしまいます。
- 嫌われたらどうしよう。。。
- こう思われたらどうしよう。。。
- いじわるやいじめにつながったら。。。
などの思いから不安や心配が出てきて集団に対しての苦手意識が強くなります。
逆に人の目を気にしなさ過ぎて問題になることもあります。
人の目を気にすることでモラルやルールの理解が深まります。
そのため人の顔色や雰囲気を察知する力も集団適応には必要なスキルかもしれません。
人の目が過剰に気になる場合は、カウンセリングや心理療法で適切に向き合っていくと自然とちょうどよい感覚に落ち着くことも少なくありません。(発達課題のあるお子さまでも認知的な理解ができるケースではカウンセリングや心理療法なども用います)
人の目が気にならない場合では、他者との信頼関係を築く、興味を持つ、顔色を見るなどの習慣が身についてくると変化が生まれてくることがあります。
HSCと集団への苦手さ
HSCとは、「Highly Sensitive Child」の略名で、生まれつき繊細で、感受性が高く、刺激に対して反応しやすい子供のことを意味しています。詳しくは(https://childpsychology-sst.com/hsc-nagoya/)
HSCのお子さまも
- 繊細さによって
- 感受性の高さによって
- 刺激に反応しやすさによって
集団への苦手さを形成してしまう場合があります。
自分の感じ方の特性を理解し、どのようにしていきたいかを決めていければ、そのためのできることは思っているよりたくさんあります。
心理的なアプローチや行動的なアプローチでその繊細さや感受性、反応性に変化をもたらすことができます。
精神的な影響によるもの
- 人の目が気になる
- 相手にどう思われるかが気になる
- 失敗やうまくいかないことへの恐れ
- 誹謗中傷や意地悪への不安
- トラウマや嫌な記憶から集団を回避したがる、うまく入れない
- 社交不安やコミュニケーションの難しさを感じる
- 発表が苦手
- 恥じらいに強く拒否反応する
- 怒られる怖さや苦手意識
- 孤独感や孤立感を感じる
などの精神的な影響により集団に入ることや集団行動が難しくなることがあります。
体が拒否反応で固まったり、症状が出るケースもあります。
精神的に悩む場合は、その悩みが自罰的になり、自己肯定感や自信、自尊心が低下してしまう二次的な問題もよく起こります。
カウンセリングや心理療法、時に身体アプローチを行いながら精神的な課題に対して向き合っていきます。
克服したい、改善したい欲求が高ければ奏功するケースもありますが、逃げたい・回避したい欲求が高いケースではその気持ちをくみ取りながら共同的にいかに進めていけるかがキーになります。
カウンセリングでできること
集団行動への苦手さを改善するためにカウンセリングが役に立つことがあります。
特に「精神的な課題」に対してはこの方法が第一選択になる場合が多いです。
最初は「そんなことはない!!」と言って否認していた状態であっても、理解してくれる先生と信頼関係ができてくれば、自分の集団での難しさを語り、理解され、一緒に手立てを考えていけるようになっていきます。
「カウンセリングをやってほしい」と子供さんご自身でご要望を伝えてくれる子も少しずつ増えてきました。
カウンセリングや心理療法では、
- 今後どうすればいいか?といった行動を決める(その問題が起きる前に〇〇する)
- 受け入れる力と妥協(それはそれで仕方ないか、まあいいか)
- 受け取り方(捉え方が変わると反応や気分も異なる)
- 理想やプライドへのアプローチ(プライド崩し、理想の変化)
- 乗り越える精神(先生との間で精神的に乗り越えていく)
などについて向き合っていくことがあります。
自分の心の持ちようや精神状態が変化すると見え方も変化しやすくなるものです。
当教室のカウンセリングは療育の中でも心理課題として行ったりしていますし、SSTの手法も取り入れています。
SSTでできること
本来のSSTは集団や小集団で行いますが、こちらでは個別で1対1で行う方法で用いることも多くあります。
適切な行動を学び
リハーサルを行い
フィードバックをもらい
再度リハーサルを行う
そういった中で子供たちの脳神経系の中に新しい行動への神経が伸びて、活用してもらうことで新たな行動習慣が出来上がっていきます。
時におもしろ可笑しくやっていくこともあって、楽しく取り組めるようにもしています。
集団行動が苦手なお子さま向けのアプローチ
名古屋こどもカウンセリングとSST教室は、
①療育的なアプローチ
②心理的アプローチ
③身体的アプローチ
の3つができる相談室兼教室です。
この3つを横断的に学び、統合的にアプローチしたいと思い、この教室を作りました。
集団行動はどこに行っても必要とされるものです。
その集団の中でストレスが少なく、自分なりに程よい適応ができるようになると、活動できる場所も増えていきます。
皆様のお役に立ちますようにご相談と支援にお応えしております。
自分のお子さまが集団行動に苦手さを感じているなかで少しこの記事でご興味を持ちましたら、何ができるか?を聞いてみてください。
10分無料相談を行っております。(予約は不要で直接お電話ください。繋がらなかったら掛けなおします)
お問い合わせはこちらです
場所は愛知県名古屋市昭和区川名です。詳しくはこちらへ「アクセス」
カウンセリング(心理療法)とトレーニング料金
個別セッション:6000円(約55分)
遠方の方は、お電話、LINE、TEAMS(旧スカイプ)、ZOOMなどで行うことができます。
詳しくはお電話もしくはお問い合わせフォームにご記入ください。